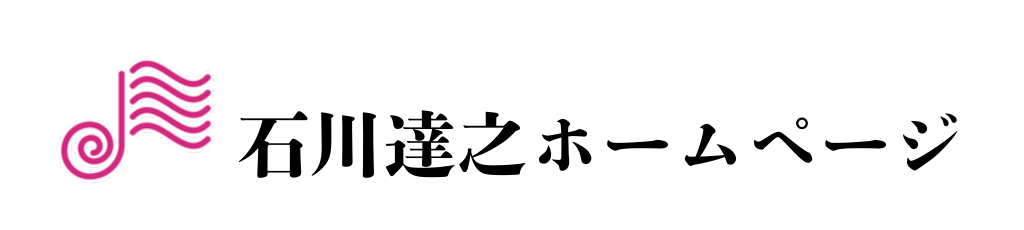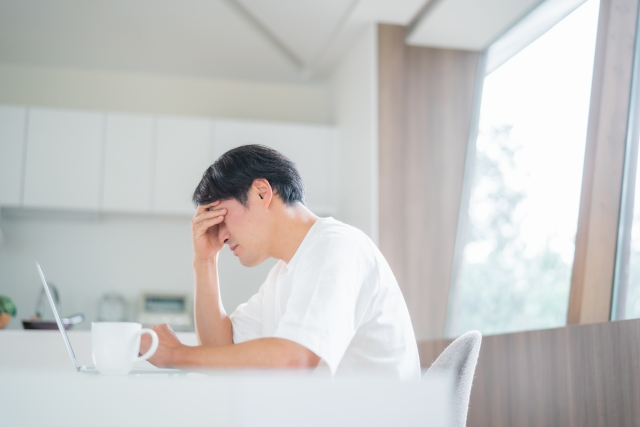ポジティブ思考– tag –
-

ネガティブ感情だって大切
生きていく上にはポジティブな感情が不可欠だが、悪者扱いされているネガティブな感情も同じくらい大切です。心の状態によっては前向きになれないこともあり、感情を簡単に分別することはできず、寂しさや悲しさも風情としてとらえる日本人の感覚からも、ポジティブ過ぎるのには抵抗を感じることさえあります。苦しみの中にいる場合は、心が回復してのちに、じっくりと出来事や自分の感情に向きあえばいいのだと思います。 -

幸せは気持ち次第
「幸せは気持ち次第」という言葉が必ずしも正しいわけではないことを書いています。ネガティブな思考をポジティブに転じるためには、心のエネルギーが一定以上必要であり、心が弱っている時に、周囲から「もっと幸せになれるはず」と言われても、心は変われないということです。思いやりを持って、相手の心の状態を理解し、かける言葉を選ぶことが大切です。
1