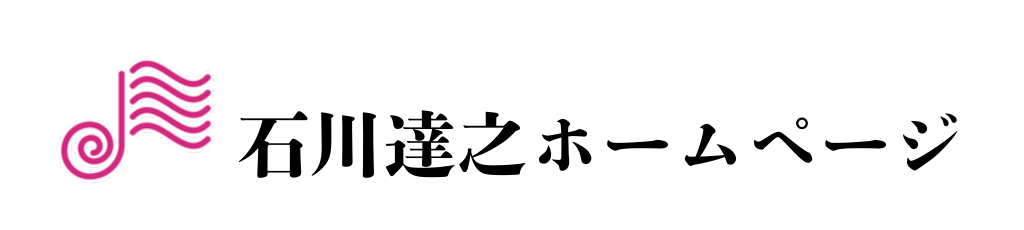方言– tag –
-

苦肉の策から方言ソング
講演の中でも方言ギャグソングを歌うことがあります。最初はただのギャグソングでしたが、方言というものがコミュニケーションツールとして有効なものであるということを知り、方言ギャグソングが多くの人に受け入れられるきっかけとなりました。私自身も、訛りに対するコンプレックスを克服し、思う存分訛りまくることができるようになりました。しかし、「おばさん」という失礼な言葉を使うことを止めたいのに、女性客からは止めないでと言われ、非常に悩ましいところです。 -

通じなかった方言
方言ギャグソングを講演で歌うことがありますが、県内ではどこで歌っても同じポイントで笑いが起こる方言曲が、県外ではまったく笑いが起こりません。県外では方言曲を封印することにしましたが、鳥取県クイズに切り替えて鳥取PRをしています。
1