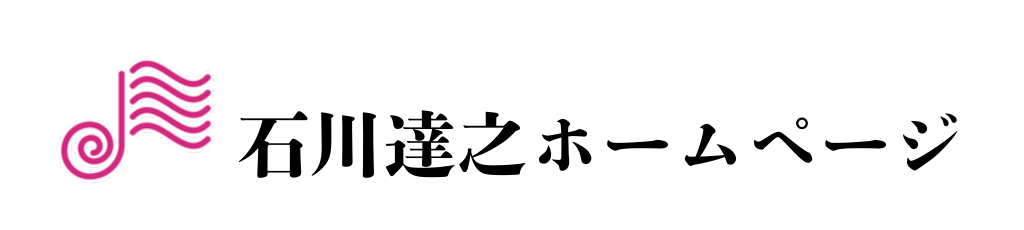家族– tag –
-

若者に話す自殺予防講演会
この記事は、私が講師を務める自殺予防講演会について書いています。救急隊員として自損行為の現場に出動した経験談を交えながら、自殺の悲惨さや家族の苦しみを伝えています。特に中学高校の生徒へ向けて、命が一番大切だということを、実例をあげて話しています。また、悩みを自分ひとりで抱えこまずに、友達や親、先生に相談することの重要性を伝えています。 -

もっと思いを言葉にして
自身が悪質ないたずらや騒ぎを繰り返していた子供時代を振り返り、満たされなかった「承認欲求」に気づきました。親になって、留守番中に子供たちが寂しいと感じていることを知り、自分自身も子供たちに思いを言葉にして伝えるようにしました。お互いに思いを言葉にして伝え合うことが大切です。 -

ありきたりの言葉だけど
講演会でありきたりな言葉だけど「生んでくれてありがとう」「育ててくれてありがとう」と言葉にすることで、心が温かくなり、心の苦しさを救ってくれるということを、消防士時代の体験と、自身の家族関係の経験とを交えて話しました。後日、感謝のお手紙などをいただくことも多いです。 -

いつか思い出になる瞬間
日常の些細な瞬間が、後に大切な思い出になることを語っています。小学生の廊下での思い出、高校生の停学、家族とのキャンプ、そして息子たちの成長を通じて、一日一日を大切に過ごすことの大切さを伝えています。 -

心を救ってくれる家族
消防職員のストレス対策についての取り組み指導から、「家族や友人を大切にする」という項目が重要であることを紹介しています。家族と一緒に過ごす時間は、心の健康に大きな助けになると述べ、自身がプチうつ状態から回復するのに家族との時間が大きな役割を果たしたことを語っています。また、労務管理を円滑に進めるためには、職員間のコミュニケーションを良好にするために、感謝を伝える努力を続けることが大切です。 -

心が前を向くまで待てばいい
母が亡くなるまで毎日病院にお見舞いに通いました。それも意識のない母が「心が前を向くまで待てばいい」と言ってくれているように思いました。母親が亡くなった後も悲しみに苦しみましたが、母親が自分を認めて愛してくれたことに感謝し、心が前を向くのを待ちながら進むことが大切だと感じました。
1