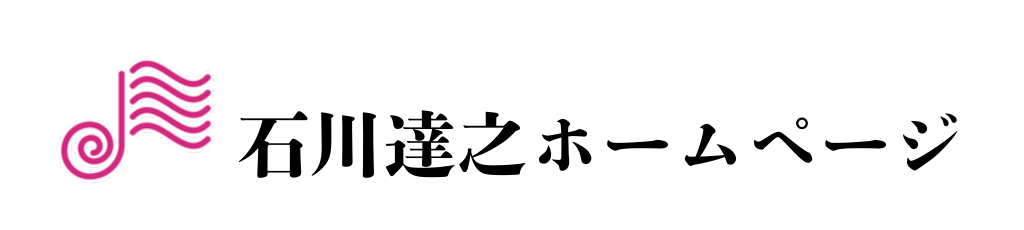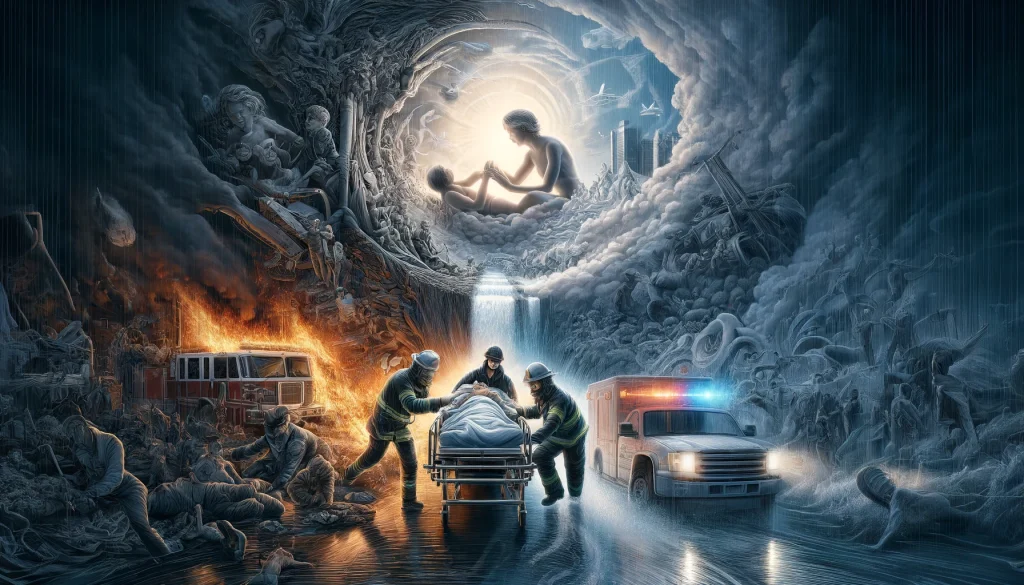火災– tag –
-

命のスゴサ
消防士として経験した火災現場や交通事故現場で見た、生命が危機に瀕した人々の姿を見てきました。これらの経験から、「命の輝き」がすべての人に宿っていることを強く感じ、命の尊さと人権について考えるきっかけになりました。講演でこの経験を話すことで、命の重さについて考えてもらっています。 -

事業所で火災にあったら【火災から命を守る避難】
この記事は、事業所での火災時の避難方法について解説しています。具体的には、一酸化炭素中毒や着衣着火による死亡事例が多いことを踏まえ、低い姿勢で避難する方法、着衣着火時の対処法、2階からの避難方法について説明しています。 -

火災・救急出動で感じる愛のある部屋とすさんだ部屋
消防士として実際の火災や救急出動してきた経験から、部屋の状態が住人の心理状態を反映していると感じることがあります。玄関から入った瞬間に感じる印象が、火災になりそうな予感や愛のある家庭であることが伝わってきたという体験を書いています。
1