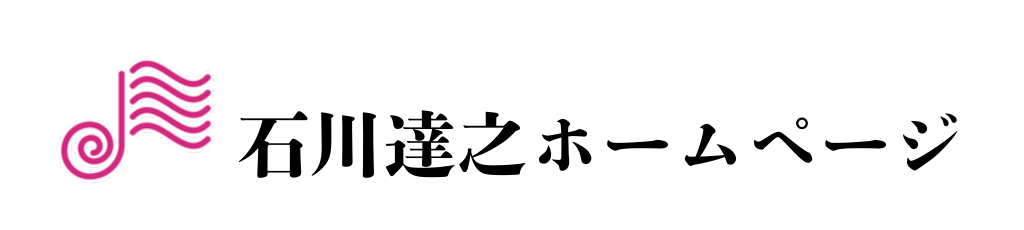最近まで講演では話さなかったエピソードがあります。
それは、火災現場や交通事故現場で私が見た、生命が危ぶまれるような状態の人たちの姿です。
一人は、まだ幼い子供で、大やけどを負っていて、皮膚に焼け溶けた衣服を付着させていました。消防隊だった私は、大声をあげて泣き叫ぶその子を、ほかの隊員と共に運び、救急隊に引き継ぎました。痛ましさで胸が張り裂けるような思いで、ストレッチャーに収容される様子を見ていました。泣き叫ぶ声は、「熱い」「痛い」「生きたい」、そう神様に訴えているように聞こえました。助かってくれ! 生きてくれ! そう祈りながら走り出した救急車を見送りました。
もう一人は女性で、交通事故で大破した車両の運転席にいました。その女性に意識はなく、救急搬送中、呼吸するたびに喀血していました。意識がないまま、眉間に皺を寄せて、苦悶の表情を浮かべては唸り声をあげ、必死に呼吸を続けようとしていました。生きることへの本能的希求のすさまじさに、ただただ圧倒され、否が応でも命の尊さに打たれずにはおれませんでした。
「命の輝き」とは、すべての人に宿っているものなのだ、と感じずにはいられませんでした。人が必死に生きようとする姿の前には、出自も、国籍も、年齢も、性別も、メジャーかマイノリティかなどということも、何の関係もありません。ただそこには、命の力があるだけです。
そんな話をどんなふうに伝えればいいのか悩みました。話すことで、もしかすると身内の方を似たような状況で亡くされた方がいたら、もっと辛い思いをさせてしまうことになるのではないかと危惧しました。それに、自分の一方的な思いで話すことは、亡くなった人たちに対して不遜な行為となりはしないか。そんなことを考え続けているうちに、絶命した人、その後力強く回復した人、あの人たちの命をかけたメッセージを、自分なりの言葉で伝えて行くことが、自分の役割ではないかと思うようになりました。
希望を持ちながら「人権」というものを考えるきっかけにしていただけるように、暗く重過ぎないようにどう伝えていくか、毎回悩みます。しかし、きれいごとではない「命の尊さ」の力を垣間見た者として、悩み甲斐を感じながら講演に臨んでいます。
(新聞の月一コラムに掲載されたエッセイです)
命の重さ、尊さを思い知らされた現場の体験を書いています。
人権講演「命の重さと輝き」