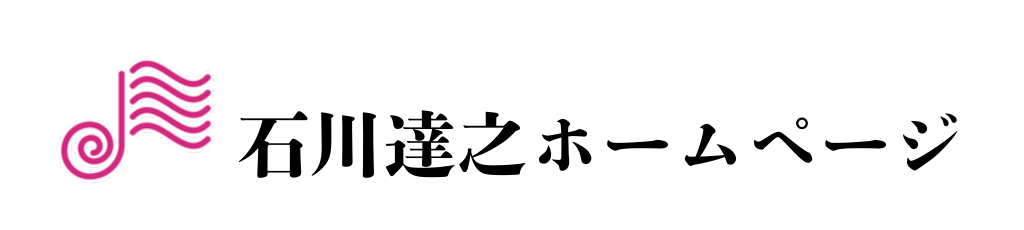コミュニケーション– tag –
-

「笑って、笑って、そして泣いた」よなご傾聴しあわせの会講演会
2025年6月21日(土)、よなご傾聴しあわせの会さん主催の講演会「心を込めてリッスン~笑って泣いて心の健康講演会」で講師を務めました。 幸せの会さんのメンバーは約20人で、会場が広いので、できればたくさんの方に参加していただきたいと、参加無料で... -

いつも安全には気をつけているのになぜ?安全大会で話すこと
この記事は、労働衛生安全大会の講演で話される内容について書いています。消防士時代に実際に出動した労災事故に関するエピソードを通じて、統計には表れてはこないものの、メンタルヘルスの問題が労働災害対策において非常に重要な要素となっています。また、良好なコミュニケーションがチームワークづくりにつながり、事故を未然に防ぐことにもつながることを救助現場で体験しました。 -

コミュニケーションと音楽
この記事は、歌入り講演を行っている心の元気講演家の石川達之が、コミュニケーションと音楽をテーマに行った研修会について語った内容です。傾聴ボランティア「あいりす」さんの連続講座の1コマとして講師を務めさせていただきました。講演会に歌を入れることで、聴衆の反応が良くなりることを実感しており、アンケートにも好評であったことが紹介されています。また、自分自身が音楽を通じて心を癒し、作品を作り続けてきた経験も紹介されています。 -

「安全管理の落とし穴」安全にチームワークは不可欠
この記事では、安全管理におけるチームワークの重要性について書いています。安全大会講演では、消防士として多くの労災事故現場に出動してきて、チームワークのほころびが事故を引き起こすことを経験しました。日頃からコミュニケーションをとり、笑顔で接することが大切であることを実例とともにお話しています。 -

そのひと言で救われる
島根県松江市にある松江市立福原会館の講演会で言葉の持つ力について話しました。言葉は、使い方によってはたったひと言が人を死に向かわせることもあれば、人の心を救うこともあります。どうせ使うなら人を苦しめることに使うのではなく、人を笑顔にしたり、元気にするために使いましょう。講演会のアンケートの感想の一部も紹介しています。 -

心配事をなくすことで交通安全を
労働災害の中の交通安全についての講演の記事です。交通事故の原因は、単なる不注意というだけでなく心の状態にも関係していることが多いのが現状です。社員同士がお互いの心身の健康状態に気を配るには、普段からストレス解消やコミュニケーションを大切にすることが必要です。
1