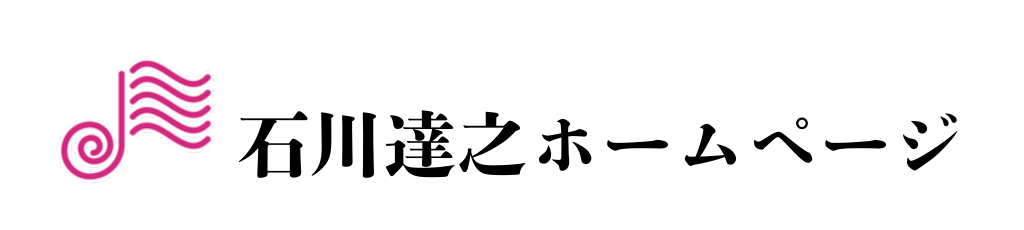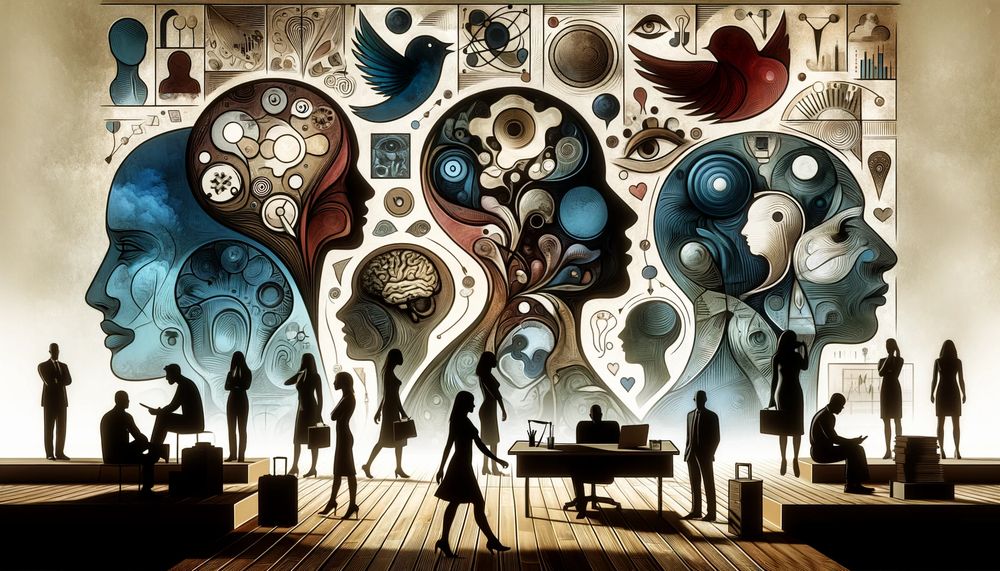人間関係– tag –
-

上から目線の友人への対処法。人間関係の見直し
上から目線の友人、マウントを取ろうとする友人への対処法。ストレスを抱えずに心地よい人間関係を築くための方法について書いています。ストレス軽減だけではなく、幸福感を感じて人生を生きるためには、人間関係の見直しが必要です。そのためのマインドについても書いています。 -

自己肯定感を確実に上げる方法5選
この記事は、心が弱った時でも自己肯定感を高め、幸福感を感じられるための方法を5つお伝えしています。日頃の小さな積み重ねがとても重要なので、この記事を読んで実践してください。 -

心を守るために自分軸を見つけよう
あなたの行動は他人の期待に左右されていませんか?自分軸を見つけることで、自分らしい選択ができ、心のバランスを保つことが可能です。他人軸で生きることで心を壊した人を、消防士時代に何人も救急搬送しました。そんな体験を踏まえて、自分軸の見つけ方について書いています。 -

嫌いな人のいい所なんて見つけられない!
誰でもどうしても苦手な人がいます。そんなことを相談すると、「相手に嫌だと感じる部分があなた自身の中にあるのよ」 「あなたにそのことを気づかせるために、あなたの前に現れたのよ」そんなことを言われます。しかし、それが全てに当てはまるわけではありません。健康的な人間関係の重要性、不快な関係からの離れ方、そして自分自身の成長と幸福に焦点を当てた時間の使い方について書いています。 -

「人生の転機」特別授業で脱サラについて話す
鳥取盲学校で行った特別授業について書いています。視力が衰えたため、今までとまったく違う業種に進まれる方たちからの質問に答えました。どうして脱サラしたのかや、脱サラ後の人との出会いで学んだこと、人とのつながりの大切さについて話しました。また、今までやってきた仕事や人との出会いは無駄ではなく、今後の財産になるということもお伝えしました。リクエストがあったのでオリジナルソングを弾き語りしました。 -

「大切」の大きさ
心にかかわるテーマの講演をしているために、いろんな方から連絡がはいります。人間関係に悩む人も多いです。大切な人を守るために存在することが当たり前ではなく「大切」に思い、扱うことです。人との関係において、相手の存在の重さや大きさを見誤ってしまうこともありますが、一日一日を大事な一瞬だととらえて、大切な人を思いやってまいりましょう。
1