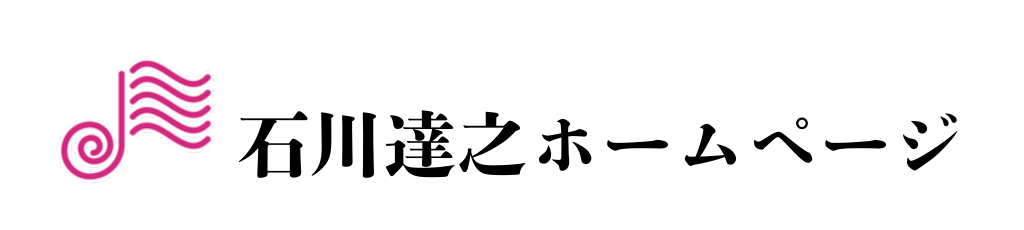安全教育– tag –
-

安全な職場はどう作る?「ミスは敵ではない」
仕事中にミスがあった場合、それを個人の問題として糾弾することの弊害、ミスを安全のための貴重なデータベースと捉えることの必要性について書いています。私がかつて勤務した消防署では、ミスがあれば激しく叱責されました。それが続き、署員全員が隠蔽体質となってしまったことで、事故になってしまった事例について、ハインリッヒの法則に関する問題点や新たな安全対策導入の必要性について書いています。 -

職場の安全は隠し事をなくすことから(子育てに似た安全教育)
この記事では、「安全について厳しく教育しているのに、なぜ事故が起こるのか?」という疑問を取り上げ、家庭での子育てと職場の安全教育に共通する点を紹介しています。子育てでの叱り方や、ミスを報告しなくなる職場の雰囲気など、具体的な例も挙げながら、ヒューマンエラーを防ぐために必要なことについて考えました。
1