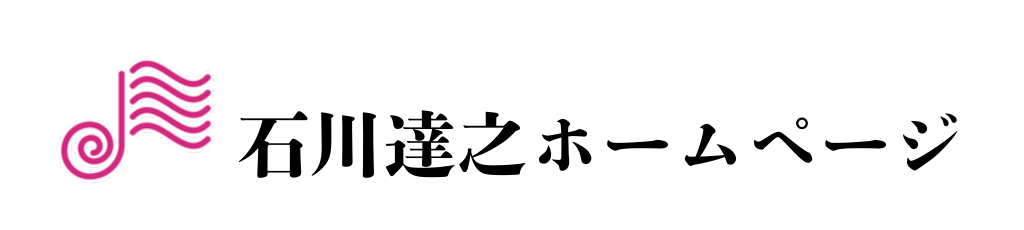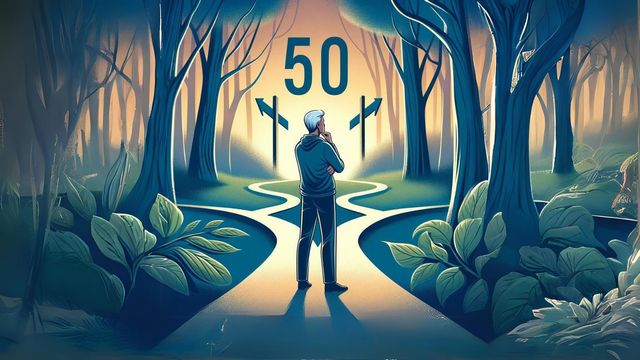脱サラ– tag –
-

あなたの経験と学びが誰かを救う(とっとり琴浦熱中小学校での授業)
2025年1月23日(土)、鳥取県東伯郡琴浦町にあるとっとり琴浦熱中小学校で授業を担当しました。 熱中小学校とは、「もういちど7歳の目で世界を…」をテーマに、大人のための学びの場を提供する地域活性化プロジェクトです。2015年に山形県高畠町で始まり、... -

50代からの人生再出発。人生はいつでも変えられる
50歳という節目に、このままでいいのかと自問自答の日々。やりたいことをやらずにいた理由に向き合い、夢を追う決意を固めた私。そのきっかけを作ってくれたのが職場の先輩の存在でした。消防士としての経験を活かし、講演を通じて多くの人々にメッセージを伝える道を選びました。 -

「人生の転機」特別授業で脱サラについて話す
鳥取盲学校で行った特別授業について書いています。視力が衰えたため、今までとまったく違う業種に進まれる方たちからの質問に答えました。どうして脱サラしたのかや、脱サラ後の人との出会いで学んだこと、人とのつながりの大切さについて話しました。また、今までやってきた仕事や人との出会いは無駄ではなく、今後の財産になるということもお伝えしました。リクエストがあったのでオリジナルソングを弾き語りしました。 -

早期退職後の講演活動が新聞に掲載される
消防を早期退職後に講演活動を開始した石川達之の「第二の人生」を日本海新聞で紹介されました。その内容をご紹介しています。 -

先輩の死が教えてくれたこと
消防士時代の先輩が定年退職を控え、これからの自由な生活を語っていた矢先に癌が発見され、数カ月後になくなりました。それが、自分自身の人生について考えるきっかけとなり、4年後に脱サラを決意しました。先輩の死を通して、人生の意義や自分がやり残すことがないように生きることを教わりました。 -

希望の歌へ
脱サラしたころの原点に帰ろうと思ったエピソードを2つ書いています。消防学校の鬼教官と再開し、交流を続けていることと、入院した晩年の母とのことが、自分をライフワークを今一度考えるきかけになりました。
1