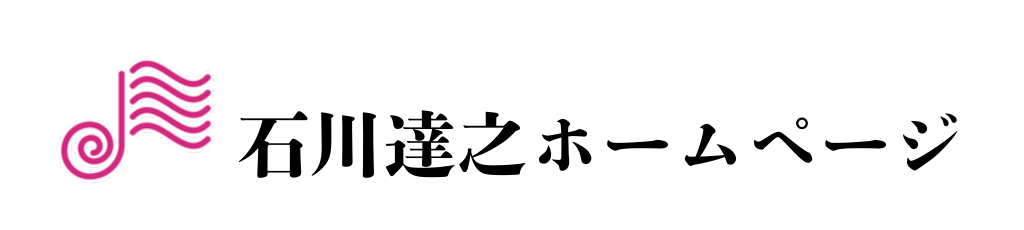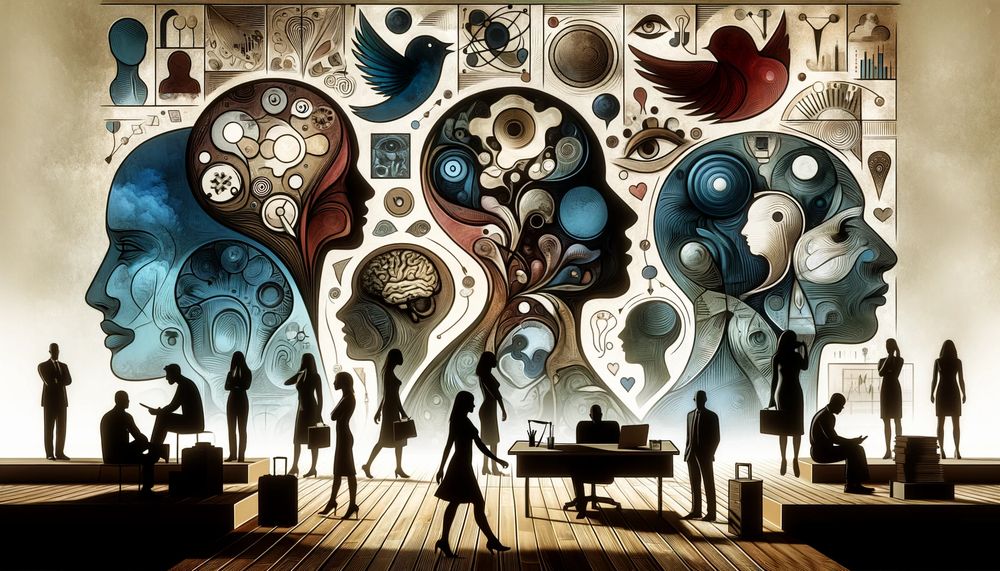ストレス解消– tag –
-

心が疲れたときに必要なのは弱音とグチ。
この記事は、日常のストレスや圧力の中で心が疲れた時、グチや弱音を吐くことの意味と重要性に焦点を当てます。社会が強いるポジティブ思考の圧力とその心への影響、そして感情の素直な表現がメンタルヘルスに与える好影響について詳しく解説しています。消防士としての経験から得た教訓や、心を優しくケアする方法も紹介されています。感情を受け入れ、表現することの大切さを通じて、読者に心の健やかさを提供する内容となっています。 -

明るく楽しく健康づくり
「琴浦町高齢者のつどい」健康講演会「明るく楽しく健康づくり」と題して、心身の健康を保つための具体的なストレス発散法についてお話しています。それらは認知機能の低下を抑えることが分かっています。また、笑いがストレス解消に効果的であり、講演では、お話とオリジナルソングの弾き語りの両方で大いに笑っていただきました。 -

在宅介護の疲れを癒やしていただきたい
在宅介護者のストレス解消について書いています。コロナ禍で家族や親戚と会えないストレスや、高齢者に感染させないために引きこもってしまうストレスが増大している中、家族や友人と話すことがストレス解消に効果的です。また、鳥取県北栄町の社会福祉センターで行われた講演会「しゃべって泣いて笑って免疫力アップ」についても紹介しています。 -

嫌いな人のいい所なんて見つけられない!
誰でもどうしても苦手な人がいます。そんなことを相談すると、「相手に嫌だと感じる部分があなた自身の中にあるのよ」 「あなたにそのことを気づかせるために、あなたの前に現れたのよ」そんなことを言われます。しかし、それが全てに当てはまるわけではありません。健康的な人間関係の重要性、不快な関係からの離れ方、そして自分自身の成長と幸福に焦点を当てた時間の使い方について書いています。 -

心の風通しをよくする時期
消防士として火災・救急現場に出動してきて、部屋の荒れ方が心の状態を反映していることに気づきました。コロナ禍でストレスが高まっているため、心の整理必要です。心の中を整理するためには、誰かと話すことが効果的です。人と会うのが困難であれば、電話、リモート会話、またSNSを利用して、悩み事やイライラを自分の心にしまい込まずに、グチをこぼしたり、悩みを話したりすることが大事です。 -

「笑顔を増やして住みよい町に」を社会福祉協議会の職員さんに
この記事は、社会福祉協議会の職員向けに、ストレス解消法と笑顔を増やす方法について説明しています。講演者は、自身の経験をもとに、笑いが心身の免疫力を高めることを説明しました。また、ストレス解消に効果的な趣味についても説明しました。 -

心の声を聞くこと
2016年10月に鳥取中部地震があった直後に書いたものです。あれほどの揺れを体験したのですから、誰の心も無傷ではいられません。収束したという実感が得られるまでは、気持ちが続くのではないでしょうか。その中に、イライラしたり、過敏になったり、不安になったり、気持ちがどんよりと曇りがちになったりすることは、心が弱いのではなく、当たり前のことです。自分のできることをやり、身内や友人と話し合うことが大切で、自分自身の心の声を聞くことも重要です。 -

心配事をなくすことで交通安全を
労働災害の中の交通安全についての講演の記事です。交通事故の原因は、単なる不注意というだけでなく心の状態にも関係していることが多いのが現状です。社員同士がお互いの心身の健康状態に気を配るには、普段からストレス解消やコミュニケーションを大切にすることが必要です。 -

「笑い」のチカラ
この記事は、笑いの大切さについて書いています。介護者や企業、お寺、公民館など、様々な団体から「笑い」に関する講演依頼を受けますが、ストレスが蓄積することが多い日々を送る中でも、笑いを見つけ、取り入れることでストレスを解消し、心身の健康を保つことができます。また、自己開示を伴う「笑い」はコミュニケーションにおいても優れたツールです。
1