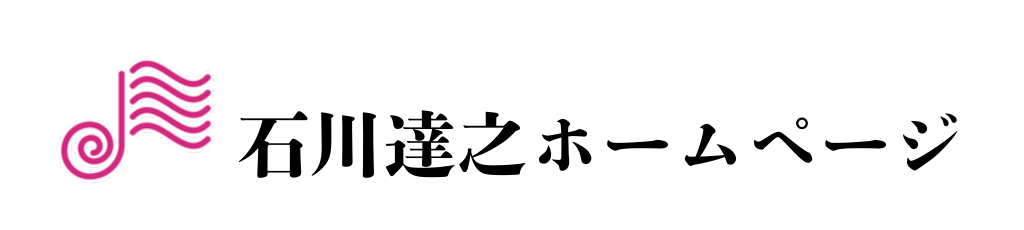「いつ消防士を辞めようと思いましたか?」と、あるラジオ番組で問われたとき、指を折って年数を数えると、決意してから実際に辞めるまでに4年が経過していました。
その頃、私生活では、家族の病気に悩みながらも、勤務のかたわらライブ活動を続け、NPO活動や自主イベントの主催などもやっていました。
時間を思うように使えないジレンマがあり、できれば思いっきり活動したいという思いがありました。
仕事の面では、職場環境も次々改善され、私が入ったころとは比較にならないほど快適なものになっていて、職場の人間関係も良好でした。
辞めて自由に活動したいという思いも現実味を帯びることはありませんでした。
そんなとき、同じ署に勤務する先輩が病気になりました。
定年退職を間近に控え、退職後の自由な生活を語っていた先輩でしたが、毎年人間ドックは欠かさず受診していたのに、大きな病に冒されていました。
しばらくは仕事を続けながら通院していましたが、その間にも痩せて、だんだん元気がなくなりました。
仕事柄、目の前で息を引き取る人をたくさん見てきました。
そのつど、胸ふさがれる思いになり、自分の生き方を問いました。
しかし、すぐにまた次の出動があり、慌ただしい生活の中で、そんな思いも次第に薄らいで行くのが常でした。
それに、消防を辞めてほかの職業に就くことは、自分の人生を捧げて真摯に仕事に向き合っている同僚たちに対して、とても失礼なことではないか、という思いもありました。
先輩は、辞令交付式では、病床にあって退職辞令を受領することはかないませんでした。
そして、その数か月後に他界しました。
同じ署で勤務し、文字通り寝食を共にした仲間が亡くなったという事実が、もう一度自分の生き方を考えさせてくれました。
おそらく世間的には、公務員という安定した職業を捨て、歌や講演など一般的ではないことを職業にしようとすることを、ばかげた選択だとみられることでしょう。
しかし、人からどう見られるかということや経済的不安も含めすべてを取り払って、自分が明日死ぬとしたら、やり残したと後悔することはないだろうかと、リアルに考えることができました。
時には「石川君、今のままでええか?」という先輩の声が聞こえる気がしました。
脱サラを決心してから実行に移すまでの4年間、一度も心が揺らがなくなっていたのは、先輩のおかげだと、今でも感謝しています。
春になると毎年その先輩のことを思い出します。
(新聞の月一コラムに掲載されたエッセイです)
こちらの記事にも先輩の死をきっかけに早期退職に踏み切ったときのことを書いています。
50代からの人生再出発。人生はいつでも変えられる