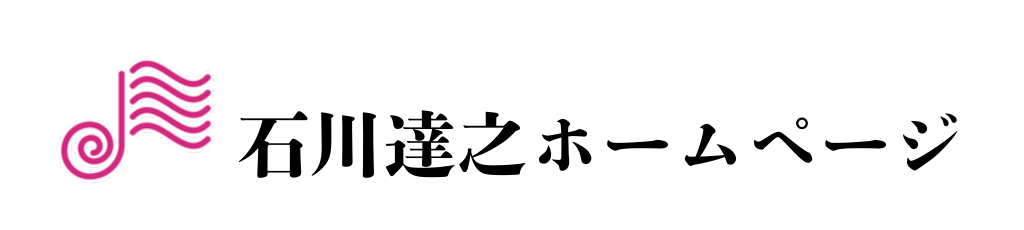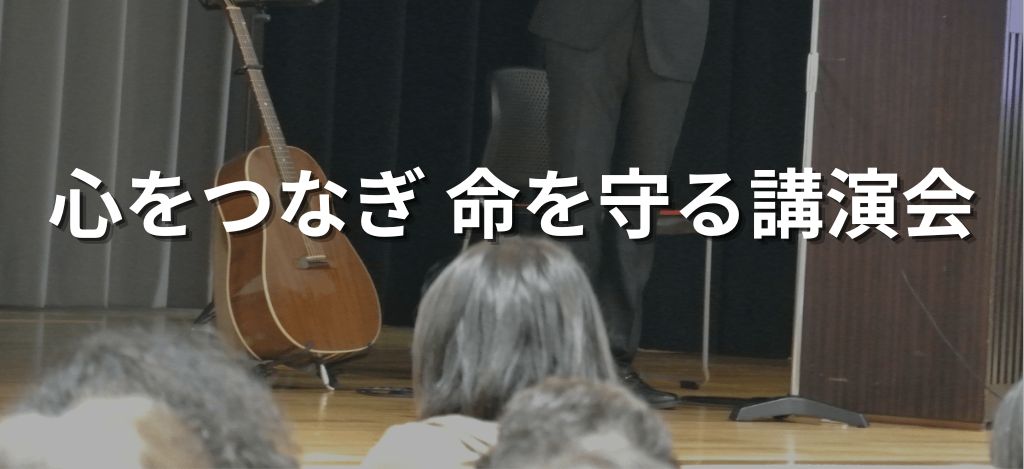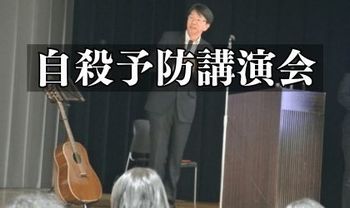命の尊さを伝え、希望の光を灯す
近年の統計が示すように、日本の自殺者数は再び増加傾向にあります。
2020年以降、11年ぶりに自殺者数が増加に転じ、特に女性や若年層の自殺が顕著に増加しています。
2022年の速報値では21,584人と、依然として高い水準を維持しています。この数字の背後には、一人ひとりのかけがえのない人生があります。
私は32年間、救急隊員として最前線で活動してきました。その間、数え切れないほどの自損行為の現場に出動し、命と向き合ってきました。
統計上の数字以上に、現場で感じる実感は重く、一つひとつの現場で、「こんなにも多くの方が自ら命を絶とうとしているのか」という痛切な思いを抱き続けてきました。
コロナ禍とその後の社会変化により、多くの人々が不安や孤独を感じています。だからこそ今、自殺予防の取り組みがより一層重要になっているのです。
この経験は、単なる職務上の記憶ではありません。
私自身、親しい友人や大切な親族を自殺で失うという、深い悲しみを経験しています。
そのため、現場での対応は他の隊員とは違う、特別な重みを持っていました。
遺体にすがりつく家族の姿に、かつての自分たち家族の姿を重ね、「他人事ではない」という強い意識を持って対応してきました。
なぜ今、この講演会が必要なのか

増加する若者の自殺リスク
近年、SNSに自殺願望を投稿する中高生が増加しています。
その中には、実際に事件に巻き込まれるケースも少なくありません。若者たちが直面する現代特有の問題に、私たち大人がどう向き合うべきか、真剣に考える必要があります。
言葉の持つ力
私の経験から、たった一言で人生が大きく変わることを幾度となく目の当たりにしてきました。
知人のちょっとした一言で「死」を選んでしまった人がいる一方で、友人の温かい言葉で思いとどまった人もいます。言葉の持つ力、そしてコミュニケーションの重要性を改めて認識し、共有する必要があります。
社会全体の不安と向き合う
日本財団の調査によると、成人の4人に1人が「本気で自殺したいと考えたことがある」と回答しています。
先の見えない不安が社会全体を覆う今だからこそ、命の大切さ、生きることの尊さ、そして生きていることのありがたさを再確認する機会が必要です。
講演会の特徴:心に響く言葉と音楽

言葉は、人を救うこともあれば、深く傷つけることもある両刃の剣です。この講演では、言葉の持つ力について、さらに踏み込んだ内容をお伝えします。
救いの言葉
友人や家族のたった一言で、自殺を思いとどまった実例をお話しします。
たとえば、「ごめんね」という謝罪の言葉、「好きだよ」という愛情の言葉、「大切だよ」という存在を認める言葉。
どんなに小さな言葉でも、自分の心や相手の心を知ろうとする思いから生まれた言葉には、とても大きな価値があります。
心を傷つける言葉
普段何気なく使われている言葉が、相手の心の状態によっては深い傷になることがあります。
実際に私が出動した自損行為の現場で、こんなケースがありました。
心の病気で自宅療養している人に、親戚の方が
「いつまでここでゴロゴロしているつもりなんだ。お前がちゃんと働いて、家族を養っていかなきゃいかんだろう。しっかりしろ!」
と言ったそうです。
そのしばらく後に、その人は自ら命を絶ってしまわれました。
「やっと元気になりかけていたのに、親戚の者が、あんな言葉をかけたせいでこんなことに」
そう泣きながら語る家族の言葉に、救急隊員であった私ギューと胸がしめつけられるような思いになりました。
他にも、
- 「頑張れ」 という励ましの言葉が、追い詰められた人にとっては重荷になった事例
- 「そんなことで悩むなんて」 という言葉が、問題を軽視されたと感じさせてしまった事例
- 「苦しいのは君だけじゃない」 という言葉が、理解されていない、突き放されたと受け止めさせて苦しめた事例
これらの実例を通じて、言葉を発する際の注意点と、相手の立場に立って考えることの重要性をお伝えします。
コミュニケーションの重要性
困難な状況にある人との効果的なコミュニケーション方法について、具体的なアドバイスを提供します。
日常生活で、相手の気持ちを気にかけてあげて、それを言葉にしてあげることはとても大切です。
仕事でのミスやトラブルがあったときに、上司や同僚から「大丈夫だよ」「君のことを信じてるよ」と言われると、自分のやる気や自信が復活することがあります。
傾聴の姿勢、共感的な対応(「つらいね」「苦しいね」「悲しいね」、適切な言葉選びなど)、実践的なスキルをお伝えします。
コミュニケーションの重要性
中学生・高校生向け講演

若い世代に向けては、特に以下のような実体験を交えながら、心に響くメッセージを伝えます。
1. 自殺の現実ーきれいで楽な死に方などない
思春期には「死」を美化する傾向もあるため、あえて現実をお伝えします。
救急種別の中に 「自損行為」 という種別があり、私は様々な手段で自殺を試みたケースに出動してきました。
いろんなケースがあり、具体的な描写は避けますが、亡くなった方の苦悶の表情を見ると、 楽な死に方やきれいな死に方はありません。
中学生の仲の良かった女子生徒が一緒に飛び降り自殺をしたというニュースも、何度か見ました。思春期には死を美化する傾向もあるので、「自分で死を選んでも、美しくないし、苦しむよ」ということを、あえてしっかりと伝えています。
2. 希望は必ずあるー「生きていてよかった!」と泣いた夫婦
自動車の排ガスで無理心中をしようとした夫婦の救急現場でのことです。
幸い、通行人の通報が早くて、どちらも助かりました。
救急隊が到着したときには、奥さんは車外に出ていて、運転席でぐったりとして意識を失っていたご主人に泣きながら声をかけていました。
2人を救急車内に収容し、意識はないものの脈も呼吸もしっかりしていたご主人に酸素投与しながら搬送しました。搬送中も、奥さんは泣きながらご主人の体にしがみついていました。
搬送途上で、ご主人が眼をひらき、意識を取り戻しました。
奥さんとご主人は、号泣しながら抱き合って喜んでいました。
「よかった! 本当によかった! 生きててよかった!」
その時の言葉は、あれからずいぶん経過しましたが、今も記憶に残っています。
自殺をしようとして一命をとりとめた人の多くがメンタルを回復され、「なんであのとき死のうと思ったんだろう」と早まった行為を後悔されます。
自殺未遂経験した私の友人も、
「当時の気持ちは、自殺して自分を殺そうなんて気持ちではなかった。生きなおしてもっとよりよく生きたいと思った」
と言っていました。
3. 家族の苦しみは計り知れない
ロープをはずし、床に横たえた遺体にとりすがって泣きじゃくる家族の姿を、何度も見てきました。
呼吸をしなくなった家族に、呼びかけ、叫び、身体を揺すぶっている様子は、救急隊員も自分の心臓をもつかんで揺さぶられているような気持ちにさえなります。
実は私も、身内が自殺しています。
残された家族の心の苦しみは一生つづきます。
だからなおさら伝えたいのです。
愛おしい家族がこの世からいなくなるなんて。
しかも、病気や怪我ではなく、そんな悲しい手段を選ぶなんて。
どうして自分は助けてあげられなかったんだろう、と自分自身をずっと責め続けるのです。
生徒たちの感想文には、
「残された家族がそこまで悲しむんだということがよくわかりました」 「家族を悲しませたくないと心から思いました」
ということを書いてくれていました。
4. 命が一番たいせつ
生活している中で、夢が破れ、目標が達成できなかったり、いじめられたり、さまざまなケースで生きる意欲を失う場面があるかもしれません。
「それでも命が一番たいせつだよ」 と、生徒たちに話しています。
なにかあったら親でも先生でも友達でも、相談しよう。
自分一人で悩み事をかかえていると、頭の中が悩み事でいっぱいになってしまう。
そうなると、君たちのことを心から愛してくれている周囲の存在さえ見えなくなるから、その前に誰かに心のうちを話そう。
そして、君たちのそばにいる誰かが、元気をなくしているようだったら、声をかけてあげてください。
難しく考えなくても、話を聞いてあげるだけでいいんだよ。
「つらいね」「苦しいね」「僕は君のそばいいるからね」
そんなふうに共感してあげてほしい。
そんな話をするので、感想文には、
「僕も、悩みは友達や両親に話してみます」
「友達が苦しんでいたら、とことん話を聞いてあげようと思います」
など、たくさんの言葉を書いてくれました。
これらの話を通じて、多感な年頃の生徒たちは食い入るように真剣に聞いてくれます。
彼らの心に、命の大切さが深く刻まれることを目指しています。
一般向け講演

一般向けの講演では、「人権講演会」や「心の健康講演会」としても開催可能です。以下のようなテーマを中心に据えます:
1. 自殺予防の社会的意義
自殺が個人の問題だけでなく、社会全体に与える影響について。
寂しさや生きづらさを抱えている人はたくさんいます。
誰かに話を聞いてもらいたいと思っても、共感してくれる人がいない人もいます。
家族と一緒に暮らしていても、子どもの話を聞いてあげていない親もいます。
子どもの悩みを、「馬鹿げたことを」と取り合わない親もいます。
日本財団自殺意識調査2017の中に、「自殺の抑制要因(自殺のリスクを抑える要因)」 についての記述がありました。
- 家族に居場所がある(家族の中での「自己有用感」が高い)
- 人間同士は理解や共感ができると考えている(「共感力」がある)
家族や大切な人に、普段から以下のことを伝えることがとても大切です:
- 苦しさへの理解:「苦しかったね」「つらかったね」
- 居場所があることを伝える:「ずっとそばにいるよ」「いつも味方だよ」
- 存在価値を認める:「あなたが大切なんだ」
2. うつ病と自殺の関係
心の健康を維持することの重要性と、周囲のサポートの必要性について。
心の病気から希死念慮の症状が現れて自損行為に及ぶケースもあります。
多くは、その時期を乗り越えれば、生きる意欲を取り戻し、死ななかったことの幸運を喜びます。
私自身がうつ病になった妻をどう支えたらいいのか悩み、模索した経験があります。
妻を救うこともできないのか、と自責の念を抱えて長い期間を過ごしました。
「死にたい」と訴えられたときのつらさは忘れることができません。
なんとかうつ病にはならなかった私ですが、絶望感と無力感に苦しみました。
それでも妻に寄り添いながら生活することで、妻は回復し、仕事にも復帰し、平穏な日々を過ごしています。
3. コミュニケーションの重要性
家族や友人、同僚とのコミュニケーションが果たす役割について。
「あの時、誰かに話を聞いてもらえていたら…」
自殺者の多くは、そう思っているのではないか、私はそんな思いを持っています。
悩みや不安で心がいっぱいになり、苦しくて大切な存在のことも見えなくなったのかもしれません。
悩みを一人で抱えてしまった場合、よけいにその危険性は増します。
張り詰めた気持ちの状態が継続しないように、少しでも緊張を緩めるためにも誰かに話したり、愚痴をこぼすことも大切です。
4. 相手の心に寄り添いケアする方法
困難な状況であっても、相手の自己肯定感を高め、生きる希望を見出す支援の方法について。
何事もない日々の暮らしの中で、大切な人に、
「ちゃんと居場所があるんだよ」 「君は大切な存在なんだ」
と伝えていくことの重要性をお話しします。
講演会の意義:希望と癒しを届ける

この講演会は、自殺予防という重要なテーマに取り組みながらも、参加者の心に希望と癒しをもたらすことを目指しています。
本人も、周囲の人間も悲しい思いをしないために、微力ながら講演活動を続けています。
一人ひとりが持つ言葉の力と、音楽がもたらす癒しの力。これらを通じて、かけがえのない命を守り、互いに支え合う社会の実現に向けて、皆様とともに歩んでいきたいと考えています。
お問い合わせ・講演依頼
地域や対象者に合わせたカスタマイズも可能です。音楽の選曲や講演内容のご要望など、お気軽にお問い合わせください。
皆様の地域で、言葉と音楽の力を通じて命の大切さを伝える機会をいただけることを、心よりお待ちしております。
参考ブログ
お電話でのお問い合わせはこちら:0858-35-4388
参加者様の感想
「自殺や命のことを題材に講演するには勇気がいると思います。笑い飛ばせるような話にできないし、暗い話にもできないし、それでも歌を交えて一生懸命、命の尊さ、言葉の大切さを話して頂けてよかったと思います。ありがとうございました」
「悲惨な現場を知っている元消防士さんだからこその言葉のパワーがあり、命の重みを感じました。素敵な歌にも感動しました。私も『ありがとう』を伝えたくなりました」
「最近、傾聴の講義を受けましたが、まさしく今日のお話にぴったりはまっていると思いました。しっかり話を聞く中で、共感と話し手の方にちゃんと話を聴いているとわかってもらえるよう、スキルをみがく努力をしたいと痛切に感じました」
「私も助けられない命がありました。ずっと心に引っかかり、今日まで生きていることがつらかったのですが、今日のお話を聞いて、生きていくことそのものが大切であると気づきました」
「いろいろな体験をしてきた中で、言葉で傷つけられたり、救われたりしたことが伝わってきました。言葉には日頃わたしたちが思っている以上の強い力があることがよくわかりました」
中学生・高校生からの感想
「残された家族がそこまで悲しむんだということがよくわかりました」
「家族を悲しませたくないと心から思いました」
「僕も、悩みは友達や両親に話してみます」
「友達が苦しんでいたら、とことん話を聞いてあげようと思います」
演題例
「救急現場で学んだ命の重さ
~心を支える人のつながり~」
『うつの家族と向き合うとき
~もしも「死にたい」と言われたら~』
「救急現場が教える命の大切さ
~人を生かす言葉の力~」
講演実績
滋賀県精神保健福祉協会、鬼北町地域自殺対策講演会(愛媛県)、枚方市自殺予防対策事業普及啓発講演会(大阪府)、加東市企業人権教育協議会(兵庫県)、井原市「こころの健康講演会」(岡山県)、能美市自殺防止対策講演会(石川県)、いのちをつなぐ総合相談会(福井県)、「眠れてますかキャンペーン」(鳥取県)、1市4町共同講演会「眠れてますか?睡眠キャンペーン」(鳥取県)、うつの家族と向き合うとき〜もしも「死にたい」と言われたら〜(兵庫県西宮市)