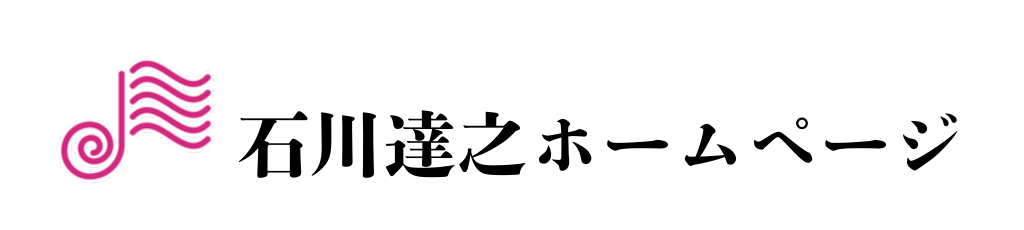人権教育– tag –
-

人生観が激変した現場体験を通して子育てと人権を
小学校保護者会の人権講演会についての記事です。コロナ差別など、心無い発言を子供がする背景には家庭での親の発言があるのではないか。救急隊として出動した現場で、心無い発言で自殺した人の家族の話を聞きました。そのエピソードも話しました。 -

「誰もが笑顔で働くために」社員研修会で人権講演会
この記事は、加東市企業人権教育協議会の社員研修会について書いています。消防士としての経験を踏まえ、心の健康の重要性についてお話しました。講演内容は、自殺予防や人権に関するものであり、ストレスや悩みに対処する方法についても具体的なアドバイスさせていただきました。新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、収録してケーブルテレビ、動画配信で多くの市民に見てもらうとのことでした。 -

オンライン講演会で「言葉の重みと命の大切さ」【人権講演会】
島根県松江市の松江市立女子高校の人権講演会をオンラインでやらせていただいた様子を書いています。講演内容は、コロナ差別でより明確になった「言葉の重み」について話し、歌った様子と、オンライン講演会でいろいろ苦労したことなどを書いています。 -

「命の尊さ」を伝えるエピソードを(長門市で人権講演会)
山口県長門市で開催されました 「第3回長門市人権教育セミナー」の講師を務めました。演題は 「救急現場が教えてくれた命の輝き~言葉は心を伝えるためにある~」で、今回は心 をあったかくしてもらいながら人権について考える時間にしていただこうと思いました。救えなかった命、あえぎ、苦しみながらも生還した怪我人、家族の愛情が痛いほど伝わってくる現場の状況など、私が人権についてより深く考えるようになるきっかけとなったエピソードを話しました。 -

「言葉にしないと伝わらない」人権コンサート
2015年2月25日、湯梨浜町で「人権トーク&コンサート」をやりました。 その時の内容を湯梨浜町報の「人権教育シリーズ」で取り上げていただきましたので、ご紹介します。 -

何人の中学生が「ありがとう」を伝えてくれるだろうか(中学で人権講演会)
島根県松江市の松江市立第2中学校での人権講演会について書いています。私自身が、救急隊員として活動した現場での体験がきっかけで、両親に「ありがとう」と伝えたエピソードを話しました。生徒たちは真剣に聴いてくれて、後日、感動的な感想文をいただいたので、その一部を紹介しています。 -

そのひと言で救われる
島根県松江市にある松江市立福原会館の講演会で言葉の持つ力について話しました。言葉は、使い方によってはたったひと言が人を死に向かわせることもあれば、人の心を救うこともあります。どうせ使うなら人を苦しめることに使うのではなく、人を笑顔にしたり、元気にするために使いましょう。講演会のアンケートの感想の一部も紹介しています。
1