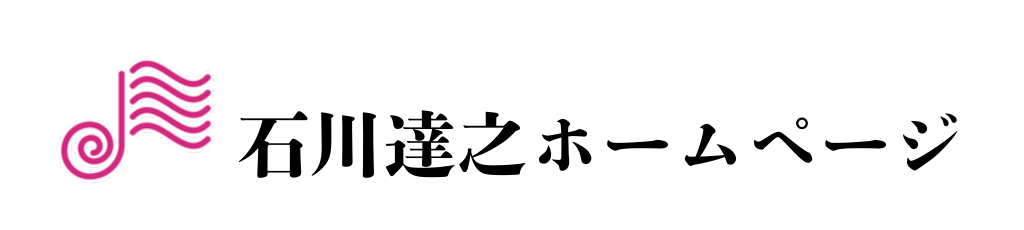幸福感– tag –
-

上から目線の友人への対処法。人間関係の見直し
上から目線の友人、マウントを取ろうとする友人への対処法。ストレスを抱えずに心地よい人間関係を築くための方法について書いています。ストレス軽減だけではなく、幸福感を感じて人生を生きるためには、人間関係の見直しが必要です。そのためのマインドについても書いています。 -

自己肯定感を確実に上げる方法5選
この記事は、心が弱った時でも自己肯定感を高め、幸福感を感じられるための方法を5つお伝えしています。日頃の小さな積み重ねがとても重要なので、この記事を読んで実践してください。 -

【感謝の力】私の人生を変えた「ありがとう」
この記事は、大切な人に「感謝」を伝えることで自分も相手も幸福感が高まることについて書いています。私自身は、感謝を伝えようと考えもしない生活を送っていましたが、消防士として活動した現場での体験から、家族の存在、一緒に過ごす時間のありがたさに気づき「感謝」を伝えるようになった体験についても書いています。 -

幸せになるために「自分の幸せは自分で決める」
自分が幸せになることを決めることの重要性について書いています。幸福感は相対的なものであり、感謝を伝えたり、他者に貢献することで高めることができます。消防士であった私は、悲しい現場を体験したことで日々の小さな幸せに気づき、自分自身が幸せであることを知りました。そんな体験も書いています。 -

幸福について考えること
近年「幸福」について心理学、経済学、脳科学などの分野で研究が進められています。日常生活ではなかなか「幸福」について具体的に考えることは少ないのですが、悲惨な救急現場に出動するたびに「生きる意味」「幸福」について考えるようになりました。年齢にかかわらずもっと「幸福」について考えてみましょう。 -

ありきたりの言葉だけど
講演会でありきたりな言葉だけど「生んでくれてありがとう」「育ててくれてありがとう」と言葉にすることで、心が温かくなり、心の苦しさを救ってくれるということを、消防士時代の体験と、自身の家族関係の経験とを交えて話しました。後日、感謝のお手紙などをいただくことも多いです。 -

「幸せ」はつかむものではなく、気づくもの
本当の幸せを見つけるためには、自分自身や周りの大切な存在に気づくことが重要であるということを消防現場で思い知らされました。上昇志向や他人との比較によって生じる満たされない心や自己否定に陥ることがあります。目の前にある幸せに気づくことが本当の幸せです。
1