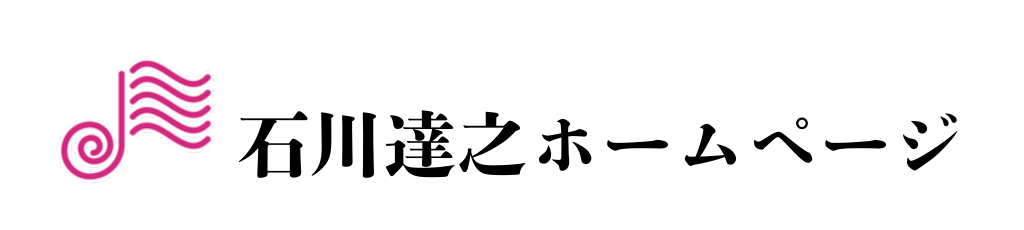音楽– tag –
-

コミュニケーションと音楽
この記事は、歌入り講演を行っている心の元気講演家の石川達之が、コミュニケーションと音楽をテーマに行った研修会について語った内容です。傾聴ボランティア「あいりす」さんの連続講座の1コマとして講師を務めさせていただきました。講演会に歌を入れることで、聴衆の反応が良くなりることを実感しており、アンケートにも好評であったことが紹介されています。また、自分自身が音楽を通じて心を癒し、作品を作り続けてきた経験も紹介されています。 -

コロナ疲れを癒やしましょう「心の元気講演会」
「コロナ疲れを癒やす講演会にしてください」と要望され、笑いと涙をテーマにした講演で講師を務めました。新型コロナの感染状況が少し落ち着いたので、コロナ疲れを癒やすために大いに笑っていただき、大いに泣いていただきました。講演は厳重な感染対策を施した上で行われました。参加された方は「やっぱり生の歌声を聴くと感動する」と喜んでくださいました。 -

「心にしみる笑いと感動」トーク&ライブショー
2015年12月6日、鳥取県湯梨浜町の中央公民館泊分館で開催された「とまり公民館まつり」でトーク&ライブショーということで出演しました。そのときの様子を日本海新聞さんの記事もご紹介しています。 -

「言葉にしないと伝わらない」人権コンサート
2015年2月25日、湯梨浜町で「人権トーク&コンサート」をやりました。 その時の内容を湯梨浜町報の「人権教育シリーズ」で取り上げていただきましたので、ご紹介します。 -

わたしの「故郷」
日本の代表的な唱歌「故郷」へのリスペクトから故郷鳥取の名産である梨の歌を作りました。自身の実家がかつて梨農家であったこともあり、都会で一人で人生を模索しながら悩む息子に「夢を忘れるな」という願いを、梨の花を象徴として作詞しました。 -

希望の歌へ
脱サラしたころの原点に帰ろうと思ったエピソードを2つ書いています。消防学校の鬼教官と再開し、交流を続けていることと、入院した晩年の母とのことが、自分をライフワークを今一度考えるきかけになりました。 -

自分を認める作業
消防士の頃、現場で悲惨な光景を目にして衝撃を受けた自分の心を、歌を作ることで癒やしました。自分の感情を認める作業だったかもしれません。歌を作ることで、自分の感情を客観的に見ることができるようになりました。講演会で歌を聴いた人たちからは、癒された、気持ちが楽になった、優しい気持ちになったという感想がいただくようになりました。 -

苦肉の策から方言ソング
講演の中でも方言ギャグソングを歌うことがあります。最初はただのギャグソングでしたが、方言というものがコミュニケーションツールとして有効なものであるということを知り、方言ギャグソングが多くの人に受け入れられるきっかけとなりました。私自身も、訛りに対するコンプレックスを克服し、思う存分訛りまくることができるようになりました。しかし、「おばさん」という失礼な言葉を使うことを止めたいのに、女性客からは止めないでと言われ、非常に悩ましいところです。 -

通じなかった方言
方言ギャグソングを講演で歌うことがありますが、県内ではどこで歌っても同じポイントで笑いが起こる方言曲が、県外ではまったく笑いが起こりません。県外では方言曲を封印することにしましたが、鳥取県クイズに切り替えて鳥取PRをしています。 -

「がんばれ」のゆくえ
講演の中でも方言ギャグソングを歌うことがあります。最初はただのギャグソングでしたが、方言というものがコミュニケーションツールとして有効なものであるということを知り、方言ギャグソングが多くの人に受け入れられるきっかけとなりました。私自身も、訛りに対するコンプレックスを克服し、思う存分訛りまくることができるようになりました。しかし、「おばさん」という失礼な言葉を使うことを止めたいのに、女性客からは止めないでと言われ、非常に悩ましいところです。 -

「生活に笑いを取り入れて」PTA人権教育講演会
2013年8月7日に鳥取県湯梨浜町立東郷小学校PTA人権教育講演会で話した内容をダイジェストで書いています。病気の家族に、親子で協力して対応してきた体験などを話しています。
1