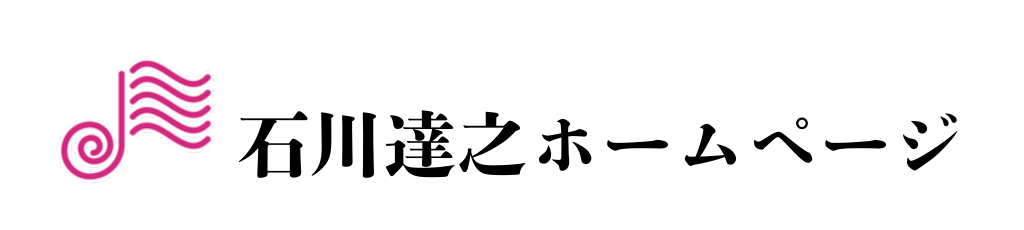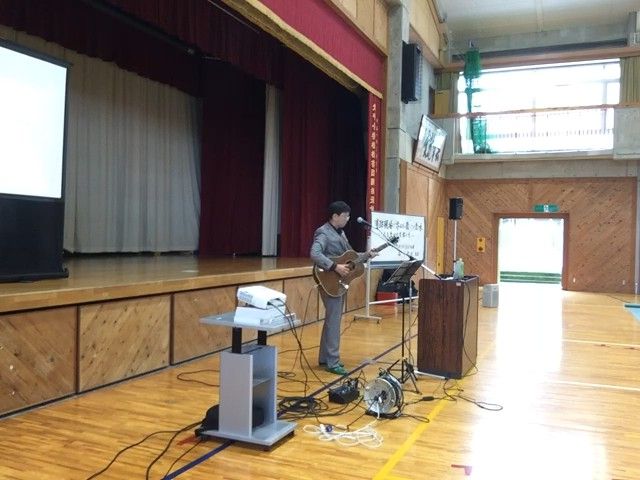保護者会– tag –
-

親子の絆を再確認 ~溝口中学校人権講演会~
昨年、2024年11月に溝口中学校での人権講演会に登壇する機会をいただきました。 中学1年生から3年生までの生徒たちと、その保護者の方々を前に、消防士として経験してきた「命の現場」での体験と、そこから学んだ家族の絆の大切さについてお話しさせていた... -

完璧を目指さない子育て
この記事は、広島県福山市の保育所での子育て講演会の内容について書いています。子育てでついつい完璧を求めてしまい、苦しい思いをしている保護者の方が多いようです。子育てに「遅過ぎる」ということはありません。気づいた時点で修正したり、思いを伝えたりしましょう。まず親が元気でいることが大切です。 -

我が子よ生まれてくれてありがとう!【中学校保護者会講演会】
ある中学校の保護者会での講演会での出来事について書いています。講演を聞いた保護者の中には、医師からまともな状態では生まれないと宣告された子どもが、無事生まれたときの喜びを思い出し、関わり方を変えようと思った人もいました。子育ては大変なこともありますが、親も子も一緒に成長していく機会にするために、子どもに向き合って楽しみましょう。 -

人生観が激変した現場体験を通して子育てと人権を
小学校保護者会の人権講演会についての記事です。コロナ差別など、心無い発言を子供がする背景には家庭での親の発言があるのではないか。救急隊として出動した現場で、心無い発言で自殺した人の家族の話を聞きました。そのエピソードも話しました。 -

子どもの反抗期は必ずやってくる
子どもの反抗期についてのブログ記事です。子どもの反抗期は、自立するために必要なものであり、親子の愛情が深ければ深いほど、反抗が強くなると言われています。私自身の経験や、多くの保護者さんから聞いた子どもの反抗期について、オリジナルソングを交えて話しています。 -

コロナ禍だからこそ「優しさ」と「思いやり」小学校PTA講演会
コロナ禍の2020年10月に行った兵庫県美方郡新温泉町の浜坂東小学校の「PTA人権講演会」で、コロナ禍でいわゆる「コロナ差別」が全国的に問題になっていました。人権意識では「思いやり」がどんなに大切なものかを、実際の救急現場の体験を通してお話させていただきました。 -

生きていることの輝き【中学生に伝える】
鳥取県伯耆町にある溝口中学校での人権講演会について書いています。命の大切さについて中学生に伝える講演を、同時に保護者の方々にも聞いていただきました。消防士時代にたくさんの死に向き合った経験から、生きていること自体がすごいことだと感じること、そして感謝を伝えることが相手だけではなく、自分の心も元気にしてくれることを伝えました。講演後に送っていた開いた生徒の皆さんの感想文の一部を紹介しています。一人ひとりが心をこめて書いてくれたのが伝わる文面ばかりでした。 -

「夢」よりもっと大切なもの(こども園保護者会講演会)
鳥取県の倉吉愛児園の保護者会で子育て講演会をやりました。講演では、夢を追いかけることの重要性と、夢が破れたときの心理的影響について話しています。たとえ夢が破れても自分自身を認め、前進するためには、子ども自身がしっかりと自己肯定感を持っていることです。親として、子どもが幼い頃から無条件の愛を伝えることが重要です。親も自分自身を大切にし、愛を与えることが、前進するための力になります。 -

親としての自分を否定しないで【保育園保護者会講演会】
社会福祉法人わかば福祉会川口西保育所で行った保護者会講演会について書いています。かわいい子どもたちも思春期になると、親として切ない思いを経験するようになりますが、それでも子どもはちゃんと親の愛情を感じ取ってくれています。そんなことを、消防士時代の現場体験を交えてお話しました。 -

「認める」「伝える」ことの大切さ
2015年7月4日の鳥取敬愛高等学校で行ったPTA研修部人権教育研修会の内容の紹介です。進路に悩む子どもさんへの対応などもお話させていただきました。また参加していただいた方のアンケート結果の一部を紹介しています。 -

子育てに行き詰まって(幼保園講演会)
鳥取市のこじか園保護者会講演会についての記事です。珍しく講演事前アンケートがあり、講演終了後にもアンケートを取られ、後日送付していたきました。悩み多き保護者さんからの感想は、講演を笑ったり泣いたりしながら聞き、子育てを家族みんなで乗り越えていけそうですという内容のものもありました。そんなアンケートの一部を紹介しています。
1