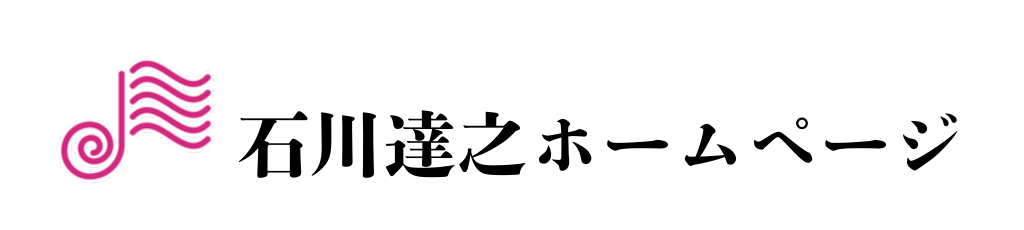子育て– tag –
-

親子の絆を再確認 ~溝口中学校人権講演会~
昨年、2024年11月に溝口中学校での人権講演会に登壇する機会をいただきました。 中学1年生から3年生までの生徒たちと、その保護者の方々を前に、消防士として経験してきた「命の現場」での体験と、そこから学んだ家族の絆の大切さについてお話しさせていた... -

おじいちゃんおばあちゃんが子育てに口を出して困るときには
「おじいちゃん、おばあちゃんが子育てに口を出して困ってます。どうすればいいんでしょうか?」 子育てや人権参観日の講演後の質疑応答に、ときどきそんな質問があります。 これはなかなか簡単には解決しない問題ですね。 「すごくストレス溜まってるんで... -

人生のリモコン
小学生時代から大人になるまでの人生の考え方の変遷を語っています。小学生時代、嫌なことから逃れたいと考え、「人生のリモコン」で時を早送りしたいと願っていました。しかし、大人になり結婚し、子供が生まれてからは、子供との貴重な時間の大切さを感じ、一分一秒が貴重なものだと気付きました。大切な人との時間や自分の存在を大切にすることの重要性について書いたコラムです。 -

完璧を目指さない子育て
この記事は、広島県福山市の保育所での子育て講演会の内容について書いています。子育てでついつい完璧を求めてしまい、苦しい思いをしている保護者の方が多いようです。子育てに「遅過ぎる」ということはありません。気づいた時点で修正したり、思いを伝えたりしましょう。まず親が元気でいることが大切です。 -

人生観が激変した現場体験を通して子育てと人権を
小学校保護者会の人権講演会についての記事です。コロナ差別など、心無い発言を子供がする背景には家庭での親の発言があるのではないか。救急隊として出動した現場で、心無い発言で自殺した人の家族の話を聞きました。そのエピソードも話しました。 -

子どもの反抗期は必ずやってくる
子どもの反抗期についてのブログ記事です。子どもの反抗期は、自立するために必要なものであり、親子の愛情が深ければ深いほど、反抗が強くなると言われています。私自身の経験や、多くの保護者さんから聞いた子どもの反抗期について、オリジナルソングを交えて話しています。 -

子育てに疲れたときには思い出そう
子育ては、楽しいばかりではなく、親としての接し方に悩んだり、時間不足によってつらいと感じることもあります。しかし、子どもたちと一緒に過ごす日々は宝物の時間です。あなたが子育てで心がけているように、自分自身を褒めてあげることも大切です。また、子育て経験者の多くが、もっと子どもたちと一緒に過ごせばよかったと後悔しています。子育てに悩んでいる方に、この記事を読んで、少しでも気持ちが楽になっていただけたら嬉しいです。 -

救急現場が教えてくれた心を元気にする方法(日本保育協会研修会)
日本保育協会中国・四国ブロック研修会での講演について書いた記事です。講演では、救急現場での活動で目にした悲惨な光景から学んだ心を元気にする方法について話し、保育士や保育園の管理職、経営者の方々のストレス解消に役立てていただけるようなノウハウを話しました。また、心の弱っている人との会話の仕方、子育てについても話しました。 -

「夢」よりもっと大切なもの(こども園保護者会講演会)
鳥取県の倉吉愛児園の保護者会で子育て講演会をやりました。講演では、夢を追いかけることの重要性と、夢が破れたときの心理的影響について話しています。たとえ夢が破れても自分自身を認め、前進するためには、子ども自身がしっかりと自己肯定感を持っていることです。親として、子どもが幼い頃から無条件の愛を伝えることが重要です。親も自分自身を大切にし、愛を与えることが、前進するための力になります。 -

夢破れても生きる力を失わないで
中高校生に講演で話す機会が増えました。大人たちは、子供たちの夢を応援するだけでなく、大きな挫折を経験した時に、生きる力を失わない強い心を育てることや生きる楽しさを伝えることが必要です。夢によってはごく限られた人しか達成できないものもあるので、たとえ夢が破れたとしても、一生懸命夢を追いかける過程で、学ぶことがたくさんあるということを伝えていきましょう。 -

無条件の愛情は裏切られない
子育ての重要性と愛情の力について書いています。自分自身や友人の経験を通じて、親子関係には無条件の愛情が必要。どんな反抗期を経ても親からの愛情が子供たちを支え、人生の大切な教訓になります。 -

もっと思いを言葉にして
自身が悪質ないたずらや騒ぎを繰り返していた子供時代を振り返り、満たされなかった「承認欲求」に気づきました。親になって、留守番中に子供たちが寂しいと感じていることを知り、自分自身も子供たちに思いを言葉にして伝えるようにしました。お互いに思いを言葉にして伝え合うことが大切です。 -

親の成長期
新思春期の子育てに悩む親に向けたもので、子育てには正解がないということを書いています。子供が成長する過程で、親も大きなストレスを感じることは自然であり、親が一生懸命考えた答えは「正解」ではないかもしれないが、「間違い」でもありません。子供の思春期は、親も子供と一緒に成長する過程です。 -

生きていることの輝き
消防士として長年にわたって数多くの事故・災害現場で活動し、多くのケガ人を応急処置して搬送しましたが、子供が大ケガをしたり亡くなったりした場合には、その光景が心に深く刻まれていて忘れられません。命の尊さを改めて感じ、「生きていてくれればいい」というのが子育ての原点になりました。 -

家族の歴史
我が家の家族の歴史について書いていますが、親元を離れていく子どもを持つ親の多くは、同じ思いを持っていると思います。息子たちが成長して巣立っていく寂しさを感じながらも、家族の絆を大切しあうことを書いています。 -

特急あさしお
今はなき「特急あさしお」をタイトルに故郷への気持ちを歌にしています。都会で暮らす同級生たちも、親が亡くなり、帰る家もなくなったという人も増えてきました。どこで暮らしても故郷や家族への感謝の思いは同じです。 -

いてくれてありがとう
人は何歳になろうと、誰かに認めてもらいたい生き物であることに変わりはありません。家族、友人、同僚、上司に認めてもらえないと、コミュニケーションがうまくいかなくなり、孤独感を抱えるようになります。そして、高校生や中学生には、友だちに「君は一人じゃない」と伝えることが大切です。存在をそのまま認める「いてくれてありがとう」という言葉で伝えましょう。 -

「認める」「伝える」ことの大切さ
2015年7月4日の鳥取敬愛高等学校で行ったPTA研修部人権教育研修会の内容の紹介です。進路に悩む子どもさんへの対応などもお話させていただきました。また参加していただいた方のアンケート結果の一部を紹介しています。 -

「個性を認める子育てを」人権問題講座
講演のテーマは「個性を認める子育てを」であり、子どもたちが自分自身を認められることが大切であることを、消防現場での体験などを交えてお話しました。講演には、親子連れや高齢者など約80名が参加し、熱心で和やかな雰囲気に包まれました。 -

子育てに行き詰まって(幼保園講演会)
鳥取市のこじか園保護者会講演会についての記事です。珍しく講演事前アンケートがあり、講演終了後にもアンケートを取られ、後日送付していたきました。悩み多き保護者さんからの感想は、講演を笑ったり泣いたりしながら聞き、子育てを家族みんなで乗り越えていけそうですという内容のものもありました。そんなアンケートの一部を紹介しています。 -

「生活に笑いを取り入れて」PTA人権教育講演会
2013年8月7日に鳥取県湯梨浜町立東郷小学校PTA人権教育講演会で話した内容をダイジェストで書いています。病気の家族に、親子で協力して対応してきた体験などを話しています。
1